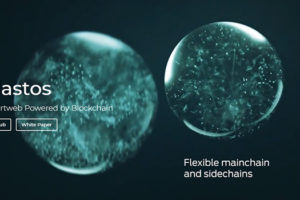BTB(BitBar/ビットバー)の概要
| 通貨名称 | BTB(BitBar/ビットバー) |
|---|---|
| 最大発行数 | 約50万枚 |
| 公開日 | 2013年5月 |
| 公式サイト | https://bitbar.co/ |
| ホワイトペーパー | – |
BTBの特徴や目指しているもの
BTBは、ほかの暗号資産と異なり日常の決済手段としての普及ではなく、価値保管を目的としている暗号資産です。2013年5月公開と、その歴史はメジャーな暗号資産よりも長い歴史があります。
BTBの仕組み
通貨には支払い・決済手段と価値尺度、価値保存という3つの役割がありますが、BTBは価値保存機能を重視した設計になっています。決済よりも決済をすることで価値を保つことがメインの役割なわけです。
こうした点では、通貨というよりも金の延べ棒などに近いものがあります。ただし、BTBは金の延べ棒と違い、決済手段としてもより容易に利用できます。
BTBの価値保存の仕組み
通貨が価値保存の役割を果たすには、通貨の発行量が十分にコントロールされていて、なおかつ発行量上限が少なく設定されている必要があります。BTBは発行量上限を約50万枚と少なくすることによって希少性を確保して、価値保存機能を実現しています。
時価総額が同じでも発行枚数が10分の1なら、単価は10倍になります。BTBはアルトコインでは初めて単価でビットコインを超えた通貨であることから、一部では有名な暗号資産です。
BTBの将来性
BTBの将来性は、現時点では乏しいと考えています。通貨としての性能は悪くなく、コンセプトも面白いのですが、そもそも価値を保存したいのならば価格が比較的安定しているビットコインでも問題ないように思えるからです。ビットコインの発行枚数も2100万枚と法定通貨と比べるとはるかに少なく、希少性があります。
公開からすでに5年も経過しているにも関わらず、取引できる暗号資産取引所が少ないのも懸念点です。Twitter上ではいまだに積極的に情報発信がされているため、開発がストップしたわけではないようですが……。
BTBが日本に上場する可能性
現時点では、日本の暗号資産取引所に上場する見通しは立っていません。すでに複数の海外の暗号資産取引所に上場していますので、気になる方はそちらを利用するといいでしょう。
BTBが購入できる海外の取引所一覧
- C-CEX
- Cryptopia