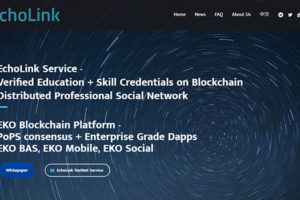目次
GRC(gridcoin)の概要
| 通貨名称 | GRC(gridcoin) |
|---|---|
| 最大発行数 | 4億2200万枚 |
| 公開日 | 2013年11月 |
| 公式サイト | https://gridcoin.us/ |
| ホワイトペーパー | – |
GRCの特徴や目指しているもの
GRCは、ブロックチェーンを用いた、マイナーに対して本当の利益を与えることを目的とした仮想通貨です。余っているパソコンの容量を用いて、容量不足に悩む世界の研究者や大学教授をサポートします。言ってしまえば空き容量のシェアリングエコノミーです。
GRCの仕組み
GridCoin(GRC)は、ビットコインを含めた他の仮想通貨と比べて環境負荷が少ないことが特徴の仮想通貨です。それを支えるのが、Proof of Research(PoR)によるコンセンサスアルゴリズムです。
これは簡単に言えば、Crossin Project IDという独自IDをウォレットにリンクさせることにより、ネットワーク内のユーザーに対して報酬を与えるシステムのことです。報酬はユーザーの平均クレジットを含む計算に比例して配分されます。
名称の由来
GridCointという名称の由来は、地球外知的生命体発見プロジェクト「@SETI」に使われていた「グリッドコンピューティング」という手法です。
グリッドコンピューティングとは、ネットワークを通じてコンピュータを連携させて、全体で高性能なシステムとして利用する仕組みのことです。非常に大雑把に言ってしまえば、安価であまり性能が高くないコンピュータを複数台ネットワークで繋いで、高性能なコンピュータのように使う技術のことです。安価なコンピュータを複数利用する仕組みであるため、ネットワーク参加者数や計算能力が変動しやすい一面もありますが、一組織では実現が難しいスーパーコンピュータやクラスタシステムなどと比べると実現可能性が高いのがメリットです。
GRDもこのグリッドコンピューティングを実現するための仮想通貨です。コンピュータの保有者は、ネットワークに対して自身のコンピュータ(=計算能力)を提供します。この計算能力を利用した人は、ネットワークに対してGRDを支払います。コンピュータの計算能力を余らせている人はそれをお金に変えられますし、不足に困っている人は安価に計算能力を確保できます。
ブロックチェーン上の投票システム
GRDはブロックチェーンをベースにした投票システムを採用しています。利用者は必要に応じて、コンセンサスに参加できます。
今まで投票で決定した事項の1つとして、Berkley Open Infrastructure Network Computing(BOINC)プロジェクトのホワイトリスト作成が挙げられます。BOINCとは、科学者や大学機関などが研究プロジェクトを進展させるため、一般からも意見を募る取り組みです。
筆者が考えるGRCの今後の将来性
現時点では、それなりに期待してもいいのではないかと思っています。グリッドコンピュータの実現に期待したいですね。
GRCが日本に上場する可能性
現時点では、日本の仮想通貨取引所に上場される見通しは立っていません。すでに複数の仮想通貨取引所に上場されていますので、機になる方はそちらで購入するといいでしょう。
GRCが購入できる海外の取引所一覧
- QBTC
- SouthXchange